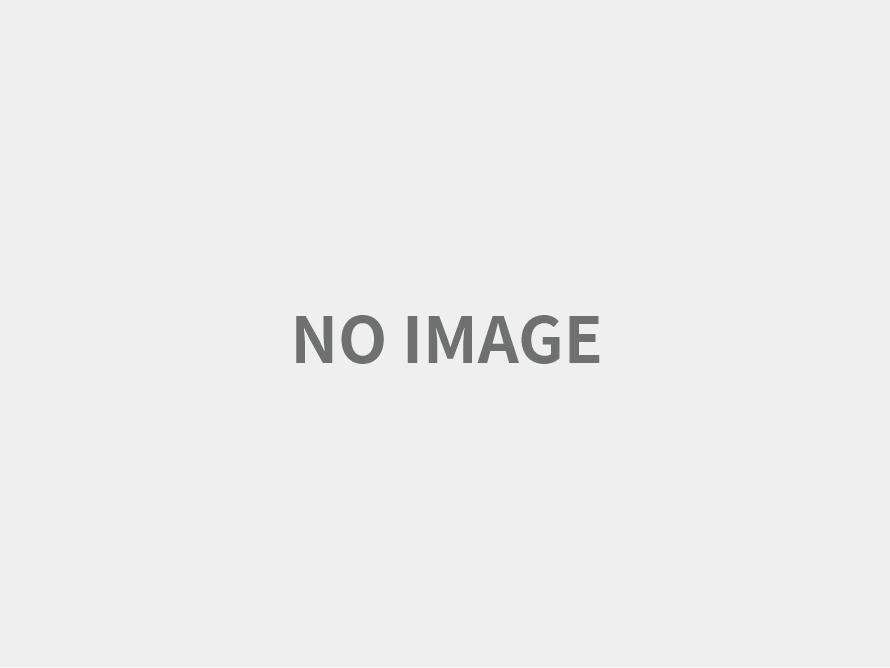地上部の病害
ねぎは作期が長く、地上部に様々な病害が同時に発生します。
4 - 5月
- やや低温の成育初期(4~5月)はボトリティス葉枯症が発生し、梅雨から盛夏期になるとべと病・さび病・黒斑病など複数の病害が発生します。
6 - 9月
- 高温期にはさび病が減り、黒斑病・葉枯病などが主となり、秋雨期に急増します。
- 黒斑病は作期を通じて発生しますが、特に8~9月頃から目立ちます。
- 高温時に播種する作型は苗立枯病(リゾクトニア菌)も注意が必要です。
- また、6~9月は高温時に発生しやすい土壌病害の軟腐病や白絹病も多くなります。
10 - 3月
- 秋~冬にかけて降雨が多いと12~4月の収穫物に小菌核腐敗病が発生します。
- 菜種梅雨の頃(3月)、べと病が発生します。
- 黒斑病は春と秋に発生が増え、共に生育後半に発生が目立ちます。
毎年発生する場所や部位を特に注意して観察
- 上記を参考に育苗期から予防散布を開始。以降、ネギの生育状況、天候、病気の発生状況等に合わせて散布隔調整、浸透移行性・浸達性のある専門剤への切り替え等を考慮しながら防除を継続。
- ねぎは温暖多湿の時期に発生する病気が多く、特に梅雨時期・秋雨時期に重点的に予防することがポイント!
-
主要病害の多くをしっかり予防できるダコニール1000※ 中心の防除体系が有効。
※ 散布での適用病害:べと病・さび病・黒斑病・葉枯病・小菌核腐敗病